【シリーズ第6話】中平コラム44:組織に“できる”を定着させるには?って話
組織に「俺たちはできる」という確信をどう育てるか?小さな成功体験と“拳合わせ”の習慣から見えてきた、組織効力感の高め方を語ります。
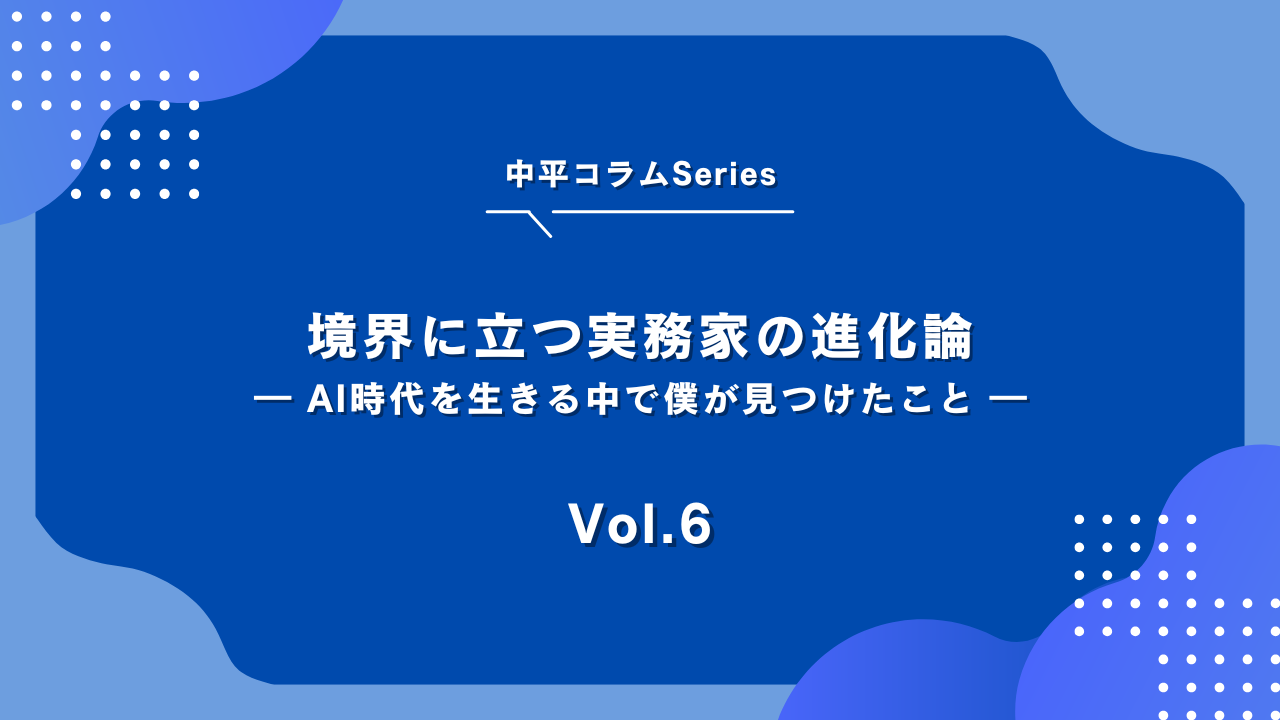
こんにちは、エスワイシステム関東の中平です。
【全8話シリーズ】
『境界に立つ実務家の進化論』 ― AI時代を生きる中で僕が見つけたこと ―
本記事(第6話)は、「組織効力感(Collective Efficacy)」についてお話しします。
↓シリーズ前回記事はこちらから↓
「【シリーズ第5話】中平コラム43:提案に立つ、橋渡し役としての責任って話」
組織効力感。ちょっと堅い言葉に聞こえるかもしれませんが、要するにこういうことです。
「俺たち、やればできるよな」って、心から思えているか?
これは僕が今、一番大事にしているチームマネジメントのキーワードです。
自己効力感は強かった。でも限界があった。
正直に言うと、僕は昔から自己効力感が高いタイプです。
「自分ならやれる」と思って動くクセがある。
でも、GIT(株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー)での経営や、今の部署に戻ってのチーム運営を経験してきた中で、
こう思うようになりました。
「個人の力には限界がある。組織全体で“やれる”と思えないと、持続しない。」
リーダーが強いだけでは、組織は育たない。
“みんなで勝てる” という感覚を育てないと、勝ち続けられないんです。
組織効力感を育てる「拳と拳」
僕が最近やっている小さな仕掛けがあります。
それが、“うまくいったときは拳を合わせる” という習慣です。
メンバーと成功を共有する。 ミスがなかったことを祝う。 想定より早く終わったことを喜ぶ。
これを、言葉じゃなくて“拳合わせ”で表現するんです。
シンプルだけど、これが本当に効く。
スポーツでも試合前にハイタッチしたり、得点後にグータッチしたりしますよね。
あれって “チームの体温” を上げるんですよ。
小さな成功体験を、身体で覚える
組織効力感って、「成功体験の積み重ね」でしか育たないと思っています。
-
できたことを認識する
-
それを仲間と共有する
-
成功体験を自信に変える
このサイクルが、チームを “俺たちやれる” モードにしていく。
逆に言うと、「成功してるのに誰も気づかない組織」って、めちゃくちゃもったいない。
拳を合わせることで、 “これは価値のある成功だ” と、身体で共有するようにしているんです。
リーダーが言語化し、メンバーが実感する
もう一つ意識しているのが、“言葉で称えること”。
「〇〇さん、ここ地味だけどすごく重要でした」
「今回、初動が早かったからトラブル回避できたよね」
「あれは “できるチーム” の動きだったよ」
こういう “内面の成功” を言葉にして伝えると、メンバーの中に少しずつ「自分たちはやれる」という感覚が芽生えていきます。
この「言語化 × 身体的共有」のセットが、僕の中での “組織効力感の育て方” です。
まとめ:「俺たちはやれる」を日常にする
組織を強くする方法は、
“大きな成果” を出すことじゃなくて、“小さな成果” を積み重ねて実感すること だと思います。
そのために、
-
拳を合わせる
-
成功を言語化する
-
自信を習慣にする
これを日常のなかに埋め込んでいく。
強い組織は、「俺たちはやれる」と思えている組織です。
そしてそれは、育てられる。仕掛けられる。伝播していく。
僕らは、そういう“自信の連鎖”をつくる側でありたい。
↓次回記事はこちらから↓
「【シリーズ第7話】中平コラム45:成功の裏側で「自分の影」に出会うって話」
著者情報

中平 裕貴(Yuki Nakahira)
株式会社エスワイシステム 関東事業本部
関東第2事業部 3SEシステム6部 事業部長代理
『技術 × 事業戦略 × 組織運営をつなぐ実務家』
エンジニアとしての技術的な知見を持ちながら、営業・事業運営・HR・組織マネジメントの視点も持つ実務家。
エンジニア、グループ会社経営、営業を経験し、技術とビジネスの両方を理解した「橋渡し役」として事業推進に携わる。
技術と組織運営をつなぎ、主体的なチームを育て、人々が「WONT TO」で動ける社会を目指す。
🛠 技術領域
アプリ開発、クラウド、データ分析、AI、
📈 事業・営業経験
SI事業の拡大、プロジェクトマネジメント、アジャイル
🏗 組織マネジメント
リーダー育成、組織改革、チームビルディング
📩 お問い合わせ・お仕事のご相談はこちらから↓
人気の記事

