【シリーズ第2話】中平コラム40:「AIと一緒に考える」というスキルの話
ChatGPTを使うほどに見えてきた、「AIと一緒に考える」という力の正体。AIをただのツールではなく、思考の“相棒”にする実践知識を語ります。
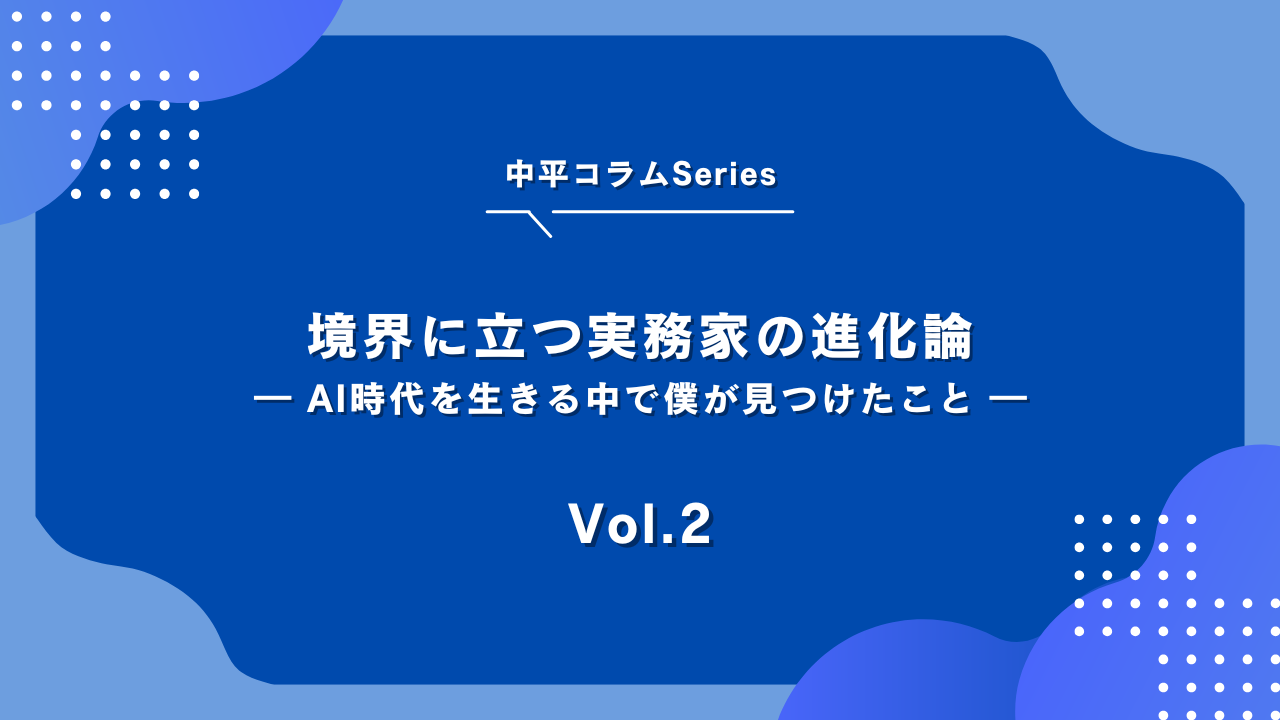
こんにちは、エスワイシステム関東の中平です。
【全8話シリーズ】
『境界に立つ実務家の進化論』 ― AI時代を生きる中で僕が見つけたこと ―
本記事(第2話)のテーマは「AIと一緒に考えるというスキル」です。
↓シリーズ前回記事はこちらから↓
「【シリーズ第1話】中平コラム39:なぜ今“コラムシリーズ”として語るのか?」
最近、「AIに置き換えられる」という話をよく耳にします。
でも僕は、「AIと一緒に考える仕事」こそがこれからの時代の本質だと思っています。
今日は、そんな“共創スキル”の話です。
AIとの出会いは、拡張の始まりだった
2023年の後半、ChatGPTに本格的に触れはじめて、正直めちゃくちゃ衝撃を受けました。
文章の要約、プログラムの整理、営業資料の構造化、議事録の起こし...。
「これ、人間の仕事じゃん」と思っていた作業の多くが、軽々と片付いていく。
最初は「すごい道具が出てきたなぁ」くらいの感覚でしたが、
だんだんと、自分の思考が “拡張されている” という感覚が強くなっていきました。
「正解を出すAI」ではなく「問いを深めるAI」
AIと一緒に作業をしていくうちに気づいたのは、
ChatGPTは “正解を出してくれる便利ツール” というよりも、「自分の問いを深めてくれる相棒」なんだということ。
例えば―
-
モヤモヤしていることを整理したいとき
-
思考の袋小路に入ってしまったとき
-
プレゼン資料の構成に悩んでいるとき
そんなときに、
「こんな問いを立ててみたらどう?」とか「その考え、こっちの視点も足してみようか」とか...
“考える相手”としてすごく有能なんです。
僕らが鍛えるべきは「問いを立てる力」
ここで重要になってくるのが、人間側のスキルです。
つまり、「AIに何を聞くか?」「どんな切り口で問いかけるか?」という部分。
これって実は、ビジネスやマネジメントでもめちゃくちゃ大事な能力なんですよね。
-
部下にどう問いかけたら気づきを得られるか?
-
お客さんにどう聞けば課題が引き出せるか?
-
自分自身にどう問いかけたら、次の一手が見えるか?
AIを活用することは、自分自身の“問い力”と向き合うということでもあるんです。
「AIとの会話」で進化するチーム
僕は最近、チームのメンバーにもAIの活用をどんどん勧めています。
プログラミング禁止、使えない人がおかしいという認知戦です。
(認知戦についての記事はこちら → 中平コラムSeries36:認知戦とは?プロジェクトにおける認知戦の活用とエンジニアの在り方って話)
でもただ単に「答えをコピペしろ」って話ではなくて、“壁打ち”に使ってほしいって話。
「この提案どう思う?」「このアイディア、整理してくれる?」
そんな軽いノリでAIと会話してみると、自分では気づけなかった視点がもらえる。
AIと会話する癖がついてくると、人との会話もレベルアップしてくるんですよね。
これは完全に予想外だったけど、実感として確かにあります。
まとめ:AIは思考の外注先ではなく、“拡張装置”である
AIに思考を丸投げするのではなく、「自分の考えを広げてくれる相棒」として使う。
それが、僕が実感している「AIと一緒に考える」というスキルの正体です。
時代は、「何を知ってるか?」から「どう問いを立てるか?」へ。
これからの仕事の価値は、“問いかける力” に宿ると思っています。
次回は、「メタファーという武器」の話。
五条悟とマーケティングを絡めた、ちょっと変化球な回です。お楽しみに!
↓シリーズ次回記事はこちらから↓
「【シリーズ第3話】中平コラム41:メタファーという武器 ─ 領域展開とマーケティングって話」
著者情報

中平 裕貴(Yuki Nakahira)
株式会社エスワイシステム 関東事業本部
関東第2事業部 3SEシステム6部 事業部長代理
『技術 × 事業戦略 × 組織運営をつなぐ実務家』
エンジニアとしての技術的な知見を持ちながら、営業・事業運営・HR・組織マネジメントの視点も持つ実務家。
エンジニア、グループ会社経営、営業を経験し、技術とビジネスの両方を理解した「橋渡し役」として事業推進に携わる。
技術と組織運営をつなぎ、主体的なチームを育て、人々が「WONT TO」で動ける社会を目指す。
🛠 技術領域
アプリ開発、クラウド、データ分析、AI、
📈 事業・営業経験
SI事業の拡大、プロジェクトマネジメント、アジャイル
🏗 組織マネジメント
リーダー育成、組織改革、チームビルディング
📩 お問い合わせ・お仕事のご相談はこちらから↓
人気の記事

