-
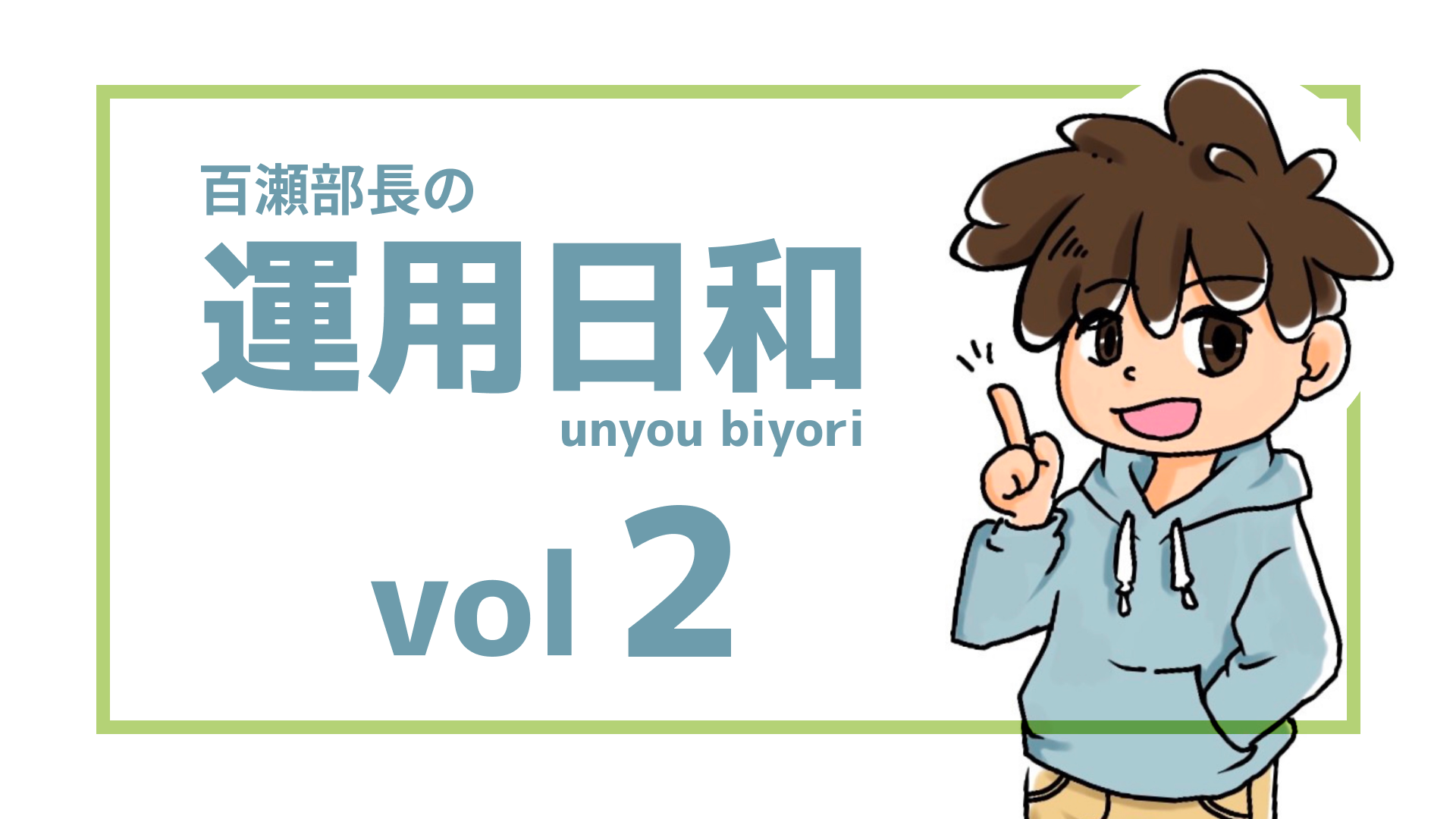
コラム
vol2. ログとHDDとサービスの未来
こんにちは、エスワイシステム関東の百瀬です。 今回はプログラムエラー時などに書き出す「ログ」に着目してお話をしていきます。 読み終わった頃にはログの大切さを実感し、エラー処理を丁寧に扱う体質になる…はず。

-
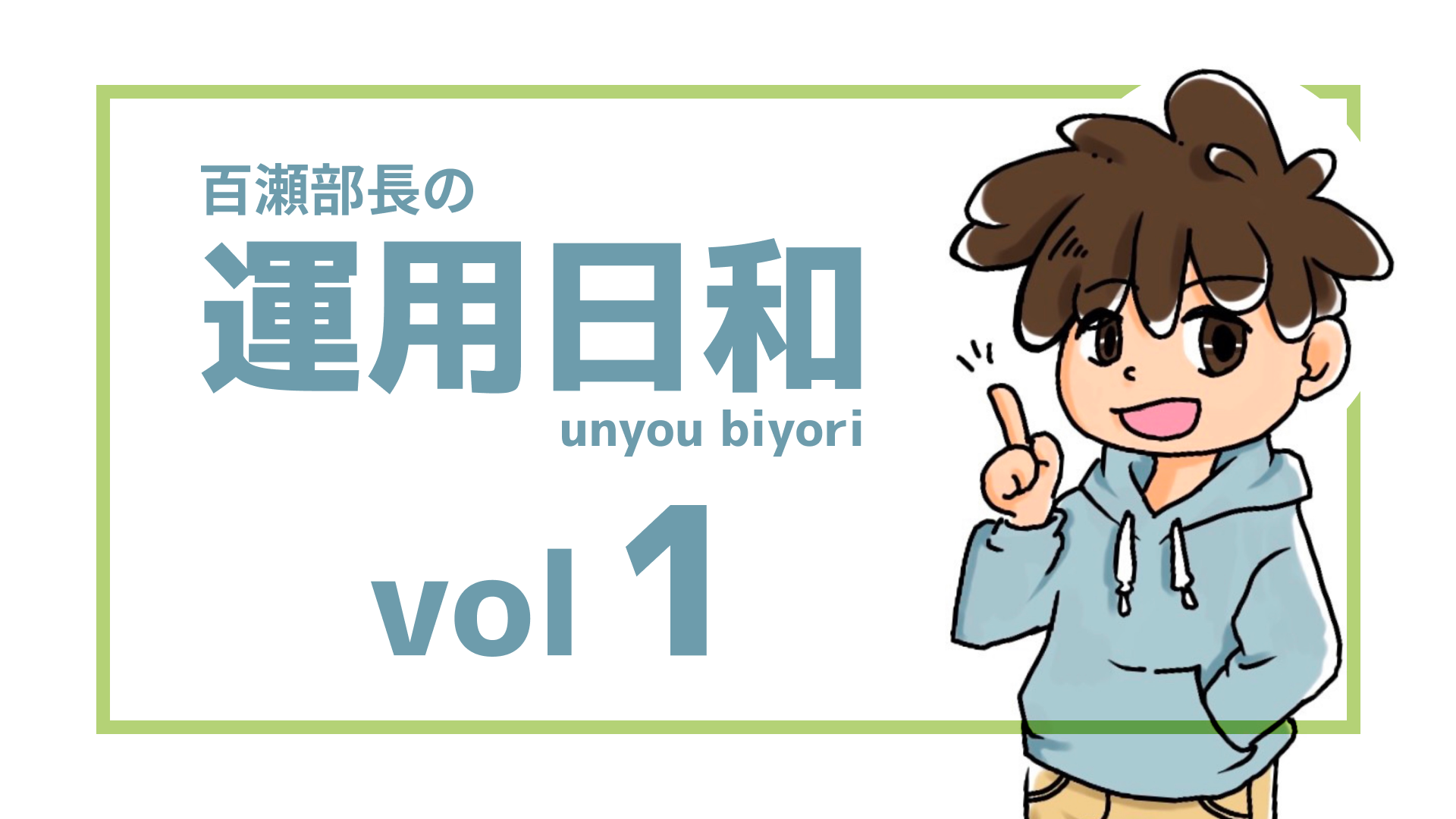
コラム
vol1. システム運用の世界への誘い
こんにちは、エスワイシステム関東の百瀬です。 今回は、私がシステム運用を始めることになった経緯と、開発者から運用者へと転身する中で感じた気付きについてお話ししたいと思います。

-

コラム
中平コラムSeries133:火消しの美学 - 緊急事態に学ぶプロジェクト立て直し術って話
「火消しの美学」とは?任せると放り投げるの違い、異変を見抜くセンサー作り、緊急時の立て直し術…。現場で学んだ実践的マネジメントを紹介。火消しを“失敗”ではなく“成長機会”に変えるプロジェクト術を解説します。

-

コラム
中平コラムSeries132:「美しい理想」が現場で嫌われる理由と、“やりたい理想”の作り方って話
「また始まった…」と白けられる“美しい理想”と、「私もやってみたい」と共感される“やりたい理想”。両者の違いは、言葉ではなく“作り方”にあった。理想が空回りする現場で見つけた5つの“逆転の鍵”を、現場のリアルとともに届けます。

-

コラム
中平コラムSeries131:組織と個人の「見えない溝」を埋める探偵思考 って話
組織の「見えない溝」はなぜ生まれる?ITリーダーが提唱する探偵思考で、管理者の頑張りが成果に直結しない難事件に挑戦。AIという相棒と共に、一週間で「なんとなくの問題」を「確実な次の一手」に変える実践プロセスを公開。3行テンプレート付き。

-

コラム
中平コラムSeries130:元探偵が辿り着いた、仕事を“楽”にする5つの思考の道具って話
「頑張ってるのに終わらない」「会議でいつも疲弊する」「そもそも何したいか分からない」――そんなあなたへ。多彩なキャリアを経て、仕事を少しだけ“楽”にするための5つの「思考の道具」を、物語とともにお届けします。

vol1. システム運用の世界への誘い
2025.09.30
コラム
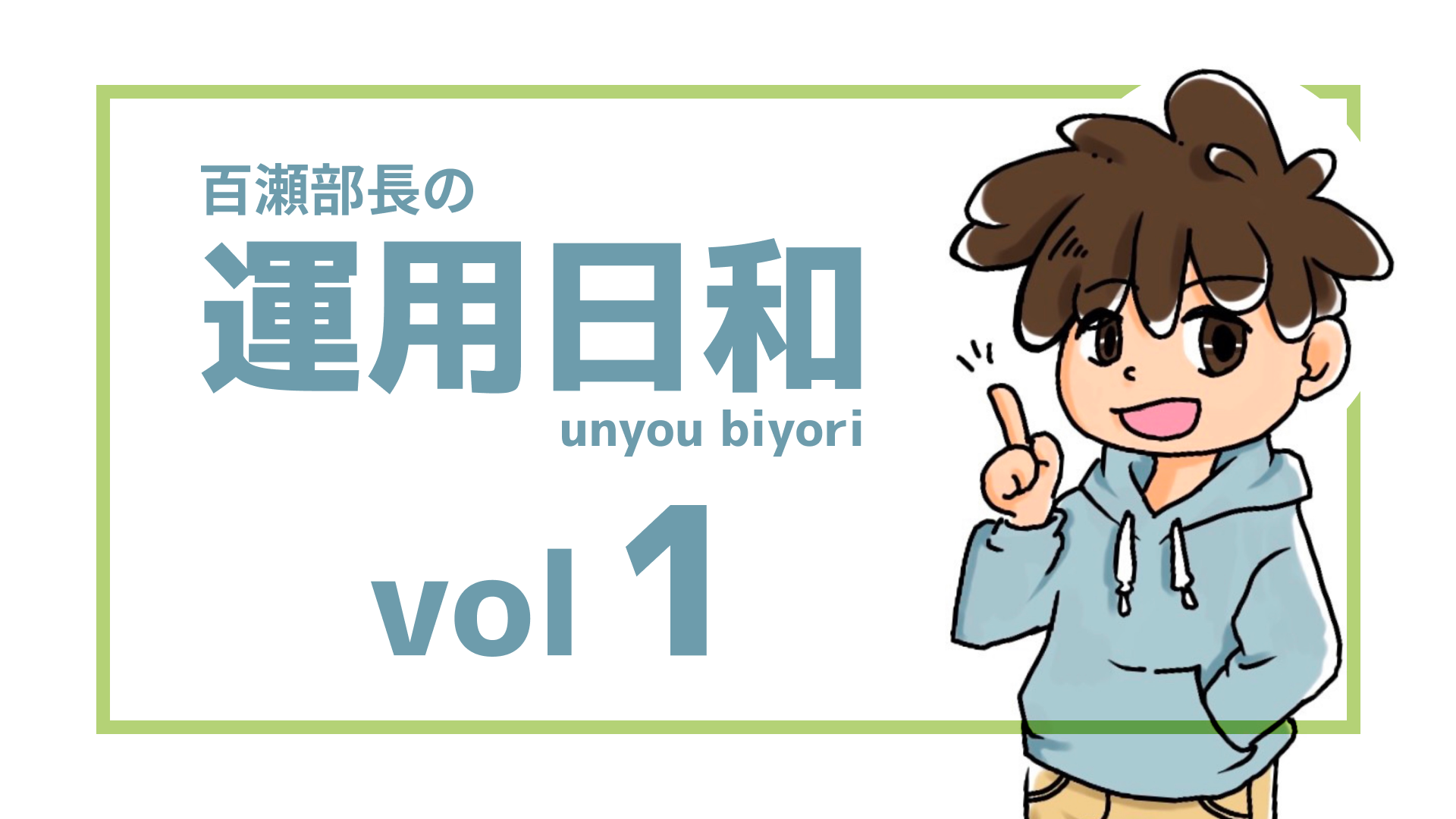
訪問いただきありがとうございます。
こんにちは、エスワイシステム関東の百瀬です。
私はシステムエンジニアとして開発業務に携わる中で、あるきっかけからシステム運用の世界に触れることができました。
システム運用は本当に奥が深く、日々気付きの連続でした。
今回は、私がシステム運用を始めることになった経緯と、開発者から運用者へと転身する中で感じた"気付き"についてお話ししたいと思います。
システム運用を始めるきっかけ
当時、私は約7年間、開発系エンジニアとして働いていました。
その頃、既存システムのハードウェア更改案件に約1年ほど携わり、案件が終盤を迎えていたタイミングでした。
そろそろ次の開発案件の話が来るだろうと思っていたところ、既存の運用メンバーが抜けたことをきっかけに「システム運用をやってみないか」と声をかけられました。
当時の私は、開発者として特筆すべき実績を残せていなかったこともあり、「やったことのないことに挑戦してみるのも面白いかもしれない」と軽い気持ちで運用の世界に飛び込むことにしました。
運用の現実と意識の転換
運用チームに入ったばかりの頃、先輩から「俺たちの仕事は開発より3倍ラクだよ」と言われました。
しかし、実際に始めてみると、すぐにそれが誤解であることに気付きました。運用には運用ならではの難しさがあったのです。
システムとサービスの違い
運用の難しさを感じた理由を自分なりに分析したところ、開発者と運用者の「プログラムに対する考え方の違い」が大きな要因であると気付きました。
開発者: 要件定義を基に新機能の開発や不具合修正を行い、「システムに新たな機能を追加すること」を主な目的とする。
運用者: 「サービスが正常に利用できるかどうか」を最優先に考え、すべての行動を「サービスに影響を与えないかどうか」の観点から判断する。
この違いを理解し、身体に覚え込ませるまでには時間がかかりました。
何度も先輩に「それは開発の考え方。運用の視点が欠けている」と指摘されました。
特に、開発チームがリリースしたモジュールの受け入れ試験を行う際、開発者の視点で試験を行ってしまい、「運用観点での試験」が不十分で何度もやり直しを求められたことがありました。
この経験は、私のITエンジニアとしてのレベルを大きく向上させる財産となりました。
今後の記事でも、こうした考え方の違いについて少しずつお伝えしていきたいと思います。
最後の門番としての責任
運用者は「サービスに影響を与えないかどうか」を最優先に考えるため、少しでもリスクがあるものは排除する傾向があります。
開発チームがリリースしたモジュールも、「本番環境を理解した上で開発されているか」を厳しくチェックし、少しでも疑わしい点があれば差し戻しや追加テストの指示を出します。
営業から「早く本番適用しろよ」と急かされることもありますが、しっかりとした受け入れ試験なしに本番適用することは絶対にありません。
仮に試験を十分に行わずに本番展開した結果、開発者が「試験はやったけど、渡したモジュールが間違っていました」と言った場合、結局クライアントから苦情を受けるのは営業です。
運用者は『最後の門番』として、本番適用の可否を判断する重要な役割を担っています。
システムの品質は「運用込み」で決まる
これは上司からの教えですが、「運用は『サービスに影響を与えないか』のさらに先の、『顧客業務に影響を与えないか』まで考えるべきだ」と指導を受けました。
システムを利用している顧客の業務を理解しているからこそ、サービス停止が顧客にどのような影響を与えるかを正しく把握し、緊急度を判断できます。その意識を持つことで、より価値のあるサービスを提供できるのです。
さらに、「システムの品質は運用の動き方で決まる」と言われたことに衝撃を受けました。それまで私は、「システムの品質は、作成したプログラムのバグの少なさで決まる」と思っていました。
しかし実際には、「運用を含めたサービスとしての評価」が品質を左右するのです。運用の仕方によって、システムの価値を上げることも、下げることもできる。
この責任の大きさに気付いたとき、恐ろしさと同時に大きなやりがいを感じました。
こうした気付きの日々積み重ねながら、私はシステム運用の世界にどんどんのめり込んでいきます。
システム運用の奥深さや、開発とは異なる視点の重要性について、これからも発信していきたいと思います。
それでは、また!

